駐車場から道路に出ようとした車とぶつかった。過失割合はどうなる?
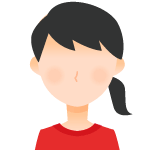 過失割合についての質問です。
過失割合についての質問です。私は、片側3車線ある幹線道路の第1車線を自動車で直進していました。
前方にある信号が赤に変わったので減速をしたところ、進路の左にあるスーパーの駐車場から相手車が道路手前で一時停止をせずに左折で道路に進入してきました。
あわててブレーキを踏みましたが、間に合わず相手車と衝突しました。
この場合の交通事故の過失割合はどうなりますか?
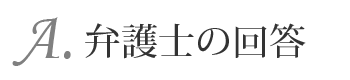
相談者の交通事故では、直進車と道路外施設であるスーパーの駐車場から左折で道路へ進入する自動車との事故となります。
そのため、基本の過失割合は、直進車:道路外出入車=20:80です。
また、相談者の走行していた道路は幹線道路であったとのことですので、直進車の過失が5%減算され、相談者車両:相手方車両=15:85をベースとして示談交渉を進めていくことになるでしょう。
一時停止がなかったという事情を徐行なしとして、証明することができれば、さらに10%の修正がなされるため、5:95の割合になる可能性も出てきます。
※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を参考にしています。
道路外出入車との交通事故
 道路外出入車とは、駐車場やガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどの道路外施設への出入りをする車両のことです。
道路外出入車とは、駐車場やガソリンスタンド、コンビニエンスストアなどの道路外施設への出入りをする車両のことです。
今回の相談者の方の交通事故のように道路外施設から右折または左折で道路に進入するときの交通事故のほかにも、道路から道路外施設へ右折で進入するときの交通事故があります。
道路の外から右折して道路の進入する場合
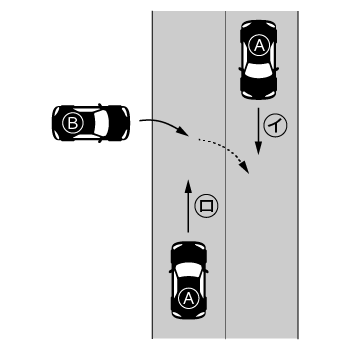
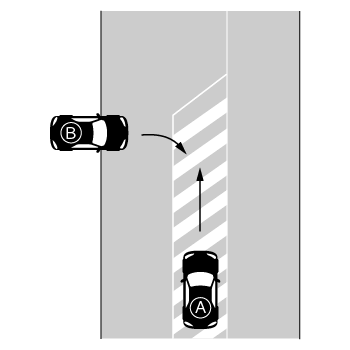
この場合の基本の過失割合は以下のとおりです。
| 直進車(A車) | 路外車(B車) |
| 20% | 80% |
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に不利に過失割合が修正されます。
| B車が頭を出して待機 | +10% |
| B車がすでに右折 | +10% |
| A車がゼブラゾーンを進行 | +10〜20% |
| A車が時速15km以上の速度違反 | +10% |
| A車が時速30km以上の速度違反 | +20% |
| A車のその他著しい過失 | +10% |
| A車のその他の重過失 | +20% |
「B車がすでに右折」している場合とは、右折を完了しているか又はそれに近い状態にあるときに適用されるものです。
㋑のケースでは、出会い頭の事故なので、この修正要素が適用されることはなく、㋺のケースでのみ適用される可能性があります。
 著しい過失とは
著しい過失とは著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
携帯電話の使用
画像を注視しながらの運転
時速15〜30Kmのスピード違反
酒気帯運転
 重過失とは
重過失とは飲酒運転
無免許運転
おおむね時速30kmのスピード違反
過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に有利に過失割合が修正されます。
| 幹線道路での事故 | -5% |
| B車が徐行していない | -10% |
| B車のその他著しい過失 | -10% |
| B車のその他の重過失 | -20% |
「幹線道路」とは、道路状況から判断されることになりますが、歩車道の区別があって道路の幅員が約14m以上(片側2車線以上)で車両が高速で走行し、通行量も多い道路が想定されています。
道路の外から左折して道路の進入する場合
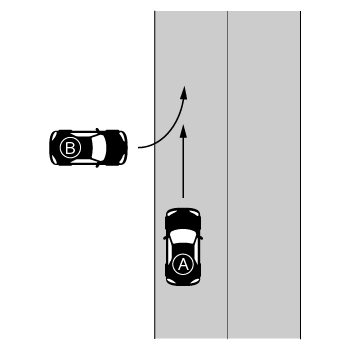
この場合の基本の過失割合は以下のとおりです。
| 直進車(A車) | 路外車(B車) |
| 20% | 80% |
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に不利に過失割合が修正されます。
| B車が頭を出して待機 | +10% |
| A車が時速15km以上の速度違反 | +10% |
| A車が時速30km以上の速度違反 | +20% |
| A車のその他著しい過失 | +10% |
| A車のその他の重過失 | +20% |
「その他著しい過失」「その他の重過失」は上記と同様です。
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に有利に過失割合が修正されます。
| 幹線道路での事故 | -5% |
| B車が徐行していない | -10% |
| B車のその他著しい過失 | -10% |
| B車のその他の重過失 | -20% |
道路外に出るために右折する場合
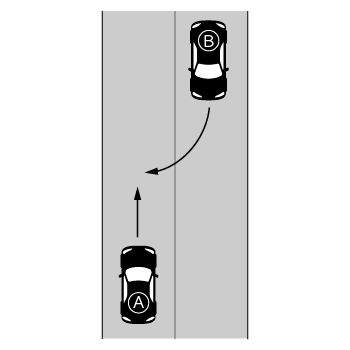
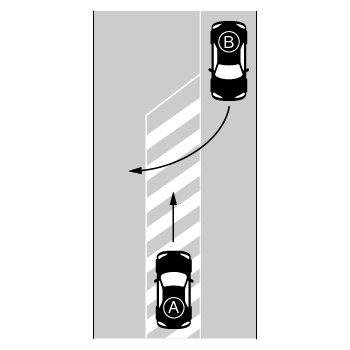
この場合の基本の過失割合は以下のとおりです。
| 直進車(A車) | 路外車(B車) |
| 10% | 90% |
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に不利に過失割合が修正されます。
| B車がすでに右折 | +10% |
| A車がゼブラゾーンを進行 | +10〜20% |
| A車が時速15km以上の速度違反 | +10% |
| A車が時速30km以上の速度違反 | +20% |
| A車のその他著しい過失 | +10% |
| A車のその他の重過失 | +20% |
「その他著しい過失」「その他の重過失」は上記と同様です。
以下の事情がある場合には、直進車(A車)に有利に過失割合が修正されます。
| 幹線道路での事故 | -5% |
| B車が徐行していない | -10% |
| B車が合図をしていない | -10% |
| B車のその他著しい過失 | -10% |
| B車のその他の重過失 | -20% |
道路出入車の過失
直進車と道路外出入車との過失を比べると、道路外出入車の過失割合が大きくなっています。
それは、道路外の駐車場やガソリンスタンド・コンビニエンスストアなどの施設や場所に出入りするための右折や左折は、Uターンや横断と同じく交通の流れに逆らう運転操作となるからです。
道路交通法上も、道路外出入車は直進車をはじめとする他の交通を妨げない注意義務があるとされています(道路交通法25条の2第1項)。
この注意義務違反は、直進車の過失より大きいとされています。
道路直進車の過失
他方で、道路を直進していた車両から、道路外から出てくる車両や道路外へ出ていく車両に注意することは可能であるため、直進車の方にも安全運転義務違反(道路交通法70条)の過失があるとされます。
過失割合の交渉のポイント

客観的な証拠を集める
交通事故の過失割合は、双方の事故態様の認識が異なる場合、争われる可能性が高くなります。
このとき、お互いによりどころとなる客観的な証拠がなければ、言った言わないの水掛け論と同じ状態になり、紛争が長期化してしまいます。
ドライブレコーダーが付いているケースでは、こうした事態を避けることができる可能性も出てきますが、それがない場合でも、道路外出入車との交通事故の場合、コンビニエンスストアやガソリンスタンドに防犯カメラが設置されていることもあります。
防犯カメラの映像は一般的に数日から1週間程度でデータが上書きされていることが多いです。
したがって、交通事故にあったらすぐに店員に声をかけて、データを保存しておいてもらうようにお願いしておくことが重要になります。
専門家のアドバイスも受ける
交通事故における過失割合は、日頃から交通事故の取り扱いをしていなければ、妥当な割合について判断することは難しいです。
そのため、保険会社との交渉をスムーズに進めるためにも、専門家である弁護士に相談してサポートを受けた方がよいケースも多くあります。


