一緒に飲酒した知人が飲酒運転した場合の責任は?【弁護士が解説】
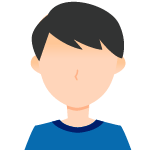 飲酒運転についての質問です。
飲酒運転についての質問です。一緒に酒を飲んだ知人が帰宅途中、飲酒運転を起こしたようです。
飲酒運転をした知人はもちろん許せません。
ところで、共に酒を飲んだ私にも交通事故の責任があるのでしょうか?
運転手と一緒に飲酒し、その後、飲酒運転をして帰宅することを認識している場合や、自宅や宿泊先へ送迎させたなどの理由がある場合には、飲酒運転の共同不法行為者(民法719条1項)または幇助者(民法719条2項)として、交通事故の損害賠償責任が追及される場合があります。
また、以下の通り刑事罰が科される可能性もあります。
運転手が酒気帯び状態と知りながら、運転手に運転することを要求又は依頼して、同乗した場合には、同乗者に対して、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(道路交通法65条4項)。
運転手が酒気帯びではなく、酒酔い状態にある場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
飲酒運転への社会的非難の強まり
 2006(平成18)年に福岡市の海の中道で発生した3児死亡飲酒事故以降、飲酒運転に対する社会的な非難が強くなっており、危険運転致死傷罪や免許の取消し、飲酒運転手の免許の再取得できるまで期間を長期化するなどの法改正が行われています。
2006(平成18)年に福岡市の海の中道で発生した3児死亡飲酒事故以降、飲酒運転に対する社会的な非難が強くなっており、危険運転致死傷罪や免許の取消し、飲酒運転手の免許の再取得できるまで期間を長期化するなどの法改正が行われています。
民間企業や公務員においても、飲酒運転した従業員や職員に対して厳しい処分を下す傾向にあります。
民事上の責任
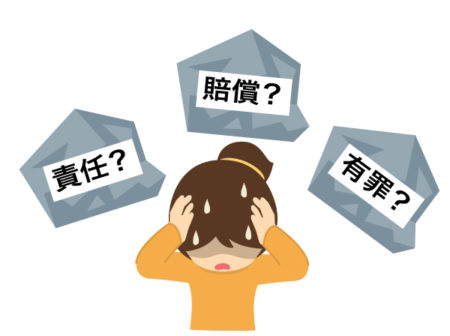 飲酒運転により、交通事故を起こして人にケガをさせた場合に、民事上の賠償責任を負うのは当然です。
飲酒運転により、交通事故を起こして人にケガをさせた場合に、民事上の賠償責任を負うのは当然です。
では、加害運転手と一緒にお酒を飲んでいた人やお酒をすすめた人、加害車両の同乗者の民事上の責任はどうなるのでしょうか。
結論としては、加害運転手とともに事故の損害賠償責任を負う共同不法行為者または幇助者とされる可能性があります。
一緒にお酒を飲んでいた人の責任
裁判例(東京地判平18.7.28)において、以下のような事情から、酒席に同席していた者の責任を認めたものがあります。
裁判所は、道路交通法65条2項が「前項に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と規定していることを踏まえて、飲酒した後に車両等を運転するおそれのある者に対して飲酒をすすめた者は、その者が飲酒後に運転することを制止すべき義務を負うと解しています。
その上で、同席者は、運転手と長時間にわたって飲酒を共にし、その結果、運転手が正常な運転ができない程度の酩酊状態で車を運転して帰宅することを認識できたとし、同席者には運転手の運転を制止すべき注意義務があったと判断しています。
こうした注意義務があるにもかかわらず、同席者は、早く家に帰って休みたかったばかりに、他の同席者を介して代行運転を頼むことを促すにとどまり、自らタクシーや代行運転を呼ぶことなく、運転手を駐車場に残したまま帰宅したことから、上記注意義務に違反し、民事上の責任を負うと判断されました。
同乗者の責任
裁判例(千葉地判平23.7.11)において、以下のような事情を踏まえて、同乗者の民事上の責任を認めたものがあります。
同裁判例は、以下の事情を指摘して責任を認めています。

 同乗者は、事故直前の飲酒・飲食に同席しており、運転手が、呼気一リットルあたり0.55ミリグラム以上になるほどの飲酒をしている場に居たこと
同乗者は、事故直前の飲酒・飲食に同席しており、運転手が、呼気一リットルあたり0.55ミリグラム以上になるほどの飲酒をしている場に居たこと 運転手が安全な運転をすることができない可能性を十分に認識していたこと
運転手が安全な運転をすることができない可能性を十分に認識していたこと 運転手の指示に基づき、加害車両の鍵を取りに自宅まで往復し、これを運転手に渡した上、加害車両に同乗していること
運転手の指示に基づき、加害車両の鍵を取りに自宅まで往復し、これを運転手に渡した上、加害車両に同乗していることこうした事情から、事故の発生について、同乗者も相当程度の積極的な加功が認められるとして、同乗者の賠償責任を認めています。
刑事上の責任
 加害運転手と一緒にお酒を飲んでいた人や加害者にお酒をすすめた人、加害車両の同乗者については、刑事処分がなされる可能性もあります。
加害運転手と一緒にお酒を飲んでいた人や加害者にお酒をすすめた人、加害車両の同乗者については、刑事処分がなされる可能性もあります。
刑事処分とは、罰金、禁固、懲役などの処罰が科されることです。
道路交通法65条4項では、運転手が酒気帯び状態と知りながら、運転手に運転することを要求又は依頼して、同乗することを禁止しています。
これに違反した場合には、同乗者に対して、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
運転手が酒気帯びではなく、酒酔い状態にある場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
また、飲酒運転により交通事故を起こしたことで、運転手が危険運転致死傷罪に問われた場合、同乗者も、その幇助犯(犯罪の手助けをすること)や、教唆犯(犯罪をするよう唆すこと)、より悪質な場合には、共同正犯(一緒に犯罪を行うこと)として処罰される可能性もあります。
このように、飲酒運転の同乗者に対しても厳しい罰則が設けられています。
自分は同乗しているだけだから大丈夫と安易に考えて、飲酒運転の車に同乗すれば、取り返しのつかない事態に陥るかもしれません。
飲酒運転の刑事責任についてより詳しく知りたい方は、こちらの弊所刑事サイト内の飲酒運転に関するページをご覧ください。
同乗者に対する行政処分
飲酒運転に同乗した場合、同乗者に対して、減点の行政処分がなされ、免許停止や、免許取消となる可能性もあります。

 酒気帯び運転(0.25mg未満)の場合
酒気帯び運転(0.25mg未満)の場合 酒気帯び運転(0.25mg以上)の場合
酒気帯び運転(0.25mg以上)の場合 酒酔い運転の場合
酒酔い運転の場合


